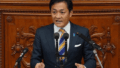はじめに
前回は法制度・在留資格の問題について取り上げましたが、制度的な課題と並んで深刻なのが、日常生活における差別・偏見・ヘイトスピーチの問題です。法律や制度がいくら整備されても、社会に根強く残る差別意識や偏見が外国人の生活を脅かし、共生社会の実現を阻んでいます。
近年、インターネット上でのヘイトスピーチが激化し、街頭でのヘイトデモも繰り返されています。また、就職や住居探しにおける差別、日常的なマイクロアグレッション(小さな差別行為の積み重ね)など、外国人が直面する差別は多岐にわたります。2016年にヘイトスピーチ解消法が施行されましたが、罰則規定がないため実効性に課題があります。
本記事では、データに基づいて差別・偏見・ヘイトの実態を明らかにし、諸外国の取り組みと比較しながら、差別のない社会を実現するための方策を提案します。
データ・統計から見る現状
深刻化するヘイトスピーチ
法務省の人権侵犯事件の統計によると、外国人に対する差別的言動に関する人権侵犯事件は年々増加傾向にあります。特にインターネット上でのヘイトスピーチが急増しており、匿名性を背景に過激化しています。
2016年に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が施行されましたが、理念法にとどまり罰則規定がないため、ヘイトスピーチは依然として続いています。特定の民族を標的にした街頭デモでは「○○人は出て行け」といった露骨な差別的言動が公然と行われ、対象コミュニティに深刻な恐怖を与えています。
川崎市では2019年に罰則付きの「差別のない人権尊重のまちづくり条例」が制定されましたが、全国的には罰則のある条例を持つ自治体は限られています。
就職・採用における差別
法務省の調査によると、外国人の約25%が就職活動で「外国人であることを理由に採用を断られた」経験があり、約40%が「日本人と同じ仕事でも賃金や待遇が異なる」と感じています。
国籍や民族を理由とした採用拒否は法律で禁止されていますが、実際には「日本人のみ募集」といった求人が存在します。また、「コミュニケーション能力」を口実に事実上の国籍差別が行われるケースや、海外で取得した学位や資格が十分に評価されないという問題もあります。
住居探しにおける差別
国土交通省の調査によると、約4割の不動産業者が「外国人の入居に拒否感がある」と回答しています。法務省の調査では、外国人の約40%が「住居を探す際に差別的な扱いを受けた」と回答しており、外国人というだけで入居を断られたり、日本人の保証人を要求されたり、礼金や敷金を高く設定されるケースが報告されています。
公営住宅においても、申請手続きの複雑さや日本語能力の要件などがハードルとなり、外国人がアクセスしにくい状況があります。
教育現場でのいじめと差別
文部科学省の調査では、日本語指導が必要な児童生徒の約10%がいじめを経験しています。日本人児童生徒と比較して割合が高く、外国ルーツであることが標的になりやすい実態が浮かび上がります。
「外国人」「ハーフ」といった呼び方での差別、容姿や言語を理由にしたからかい、仲間外れなど、様々な形態のいじめが報告されています。教員自身が多文化共生の理解や研修を十分に受けていないため、無意識のうちに差別的な発言をしたり、適切な対応ができないケースもあります。
医療機関での差別的対応
一部の医療機関では、言語の問題や医療費の未払いへの懸念から、外国人患者の診察を拒否するケースが報告されています。厚生労働省は外国人患者の受け入れ体制整備を進めていますが、対応できる医療機関はまだ限られています。緊急時に受け入れを拒否されることは、生命に関わる深刻な問題です。
諸外国の状況と比較
ドイツ:包括的な差別禁止法制
ドイツでは基本法(憲法)第3条で平等原則が定められ、人種、出身、言語などを理由とする差別を禁止しています。さらに2006年制定の「一般平等待遇法」では、雇用、教育、商品・サービスの提供など広範な領域での差別を禁止し、違反した場合の救済措置や損害賠償請求権を明記しています。連邦差別禁止庁が設置され、相談対応や啓発活動を行っています。
ナチスの歴史への反省から、ヘイトスピーチに厳格な法規制があります。刑法第130条で「民衆扇動罪」が定められ、人種や民族に対する憎悪を煽る言動は刑事罰の対象です。インターネット上のヘイトスピーチについても、SNS事業者に削除義務を課す「ネットワーク執行法」が2017年に制定されました。
カナダ:多文化主義と人権保護
カナダでは連邦レベルで「カナダ人権法」が制定されており、人種、国籍、民族、宗教などを理由とする差別を禁止しています。州レベルでも人権法が整備され、包括的な差別禁止の法制度が確立されています。
カナダ人権委員会が設置され、差別の申し立てを受け付け、調査・調停・審判を行う独立した機関として機能しています。裁判所に訴えるよりも迅速かつ低コストで救済を求めることができます。刑法でヘイトスピーチを規制しており、憎悪の扇動に対して刑事罰が科されます。学校教育において多文化主義と反差別の教育が体系的に行われ、多様性を尊重する価値観を育んでいます。
イギリス:平等法による統合的規制
イギリスでは2010年に「平等法」が制定され、それまで分散していた差別禁止関連法を統合しました。人種、民族、国籍、宗教、性別、障害など、複数の保護特性を網羅的に規定し、雇用、教育、商品・サービスの提供など幅広い分野での差別を禁止しています。平等人権委員会が設置され、差別の監視、調査、訴訟支援などを行っています。
人種や宗教などへの偏見に基づく犯罪を「ヘイトクライム」として重く処罰する制度があり、警察はヘイトクライムの統計を詳細に取り、その動向を監視しています。
日本との決定的な違い
ドイツ、カナダ、イギリスなどでは、包括的な差別禁止法が制定され、雇用、住居、教育、商品・サービスなど広範な領域での差別を明確に禁止しています。日本にはこうした包括的な差別禁止法がなく、個別の法律で部分的に対応しているにすぎません。
諸外国では差別行為に対する罰則や、被害者が救済を求める実効性のある仕組みが整備されています。日本のヘイトスピーチ解消法には罰則がなく、理念を示すにとどまっています。
カナダやイギリスには、政府から独立した人権委員会が設置され、差別事案の調査や救済を行っています。日本には国内人権機関がなく、法務省の人権擁護機関が対応していますが、独立性や権限の面で課題があります。
諸外国では学校教育を通じて、多様性の尊重や反差別の価値観を育む取り組みが体系的に行われています。日本でもこうした教育は行われていますが、体系性や継続性の面で不十分です。
今後予想される懸念
ヘイトスピーチのさらなる過激化
罰則のない現状では、ヘイトスピーチを抑止することが困難です。特にインターネット上では匿名性を背景に、より過激で悪質な言動が広がる恐れがあります。
ヘイトスピーチは対象となるコミュニティに深刻な精神的苦痛を与え、社会の分断を深めます。放置すれば、ヘイトクライム(憎悪に基づく犯罪)にエスカレートするリスクもあります。
差別の固定化と世代間継承
差別や偏見が放置されれば、社会に固定化し、次世代に継承されていきます。子どもたちが差別的な言動を日常的に目にすることで、それを当然のこととして受け入れてしまう恐れがあります。
外国ルーツの子どもたちは、差別を経験することで自己肯定感を失い、社会への不信感を抱きます。こうした負の経験は、将来的な社会統合を阻害する要因となります。
社会的コストの増大
差別により外国人が能力を発揮できない状況は、社会全体の損失です。優秀な人材が日本を避けるようになれば、経済や科学技術の発展が阻害されます。また、差別に起因する社会不安や対立は、治安や社会秩序にも悪影響を及ぼします。
解決への提案
短期的施策:法整備と救済の強化
ヘイトスピーチ解消法に罰則規定を設けるか、新たに刑事罰を含む法整備を行うべきです。川崎市の条例のように、悪質なヘイトスピーチに対して制裁を科すことで抑止力を高めることができます。インターネット上のヘイトスピーチについては、プロバイダーやSNS事業者に削除義務を課すなど、ドイツの法律を参考にした規制を検討すべきです。
外国人が差別を受けた際に多言語で相談できる窓口を拡充し、適切な救済につなげる仕組みを整備すべきです。また、企業や不動産業者への啓発を強化し、外国人であることを理由とした採用拒否や入居拒否が違法であることを明確に周知する必要があります。
中期的施策:包括的な制度構築
日本でも、ドイツやイギリスのような包括的な差別禁止法を制定すべきです。人種、民族、国籍、宗教などを理由とする差別を、雇用、住居、教育、商品・サービスの提供など幅広い領域で明確に禁止し、違反した場合の救済措置や損害賠償請求権を定める必要があります。
政府から独立した国内人権機関を設置し、差別事案の調査、調停、勧告などを行う権限を付与すべきです。イギリスのように、憎悪に基づく犯罪を「ヘイトクライム」として統計を取り、その動向を監視する仕組みを構築すべきです。
学校教育において、多文化共生と反差別の教育を体系的に実施すべきです。すべての子どもたちが多様性を尊重し、差別や偏見を持たないよう、カリキュラムに組み込む必要があります。
長期的施策:社会意識の変革
メディアは外国人に関する報道において、ステレオタイプや偏見を助長しないよう注意すべきです。一方で、外国人の貢献や成功事例を積極的に報道し、多様性の価値を伝えることで、社会の意識を変えていく役割も期待されます。
企業は多様性を尊重し、差別のない職場環境を整備する責任があります。ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを推進し、外国人が能力を発揮できる環境を作ることは、企業の競争力向上にもつながります。
差別や偏見に対抗するには、市民社会の取り組みが不可欠です。一人ひとりの市民が、日常生活の中で差別的な言動を見かけたときに、傍観せずに声を上げることが、差別のない社会を作る基盤となります。また、外国人と日本人が対話し、交流する機会を増やすことで、相互理解を深め、偏見を解消することができます。
まとめ
差別・偏見・ヘイトの問題は、外国人の尊厳を傷つけ、社会の分断を深める深刻な課題です。ヘイトスピーチ、就職や住居探しにおける差別、教育現場でのいじめ、医療機関での差別的対応など、外国人が日常生活の様々な場面で差別に直面しています。
ドイツ、カナダ、イギリスなどの先進国では、包括的な差別禁止法が制定され、罰則や救済制度が整備されています。また、独立した人権機関が差別事案に対応し、学校教育を通じて反差別の価値観を育む取り組みが体系的に行われています。
日本でも、ヘイトスピーチ規制の実効化、包括的差別禁止法の制定、国内人権機関の設置、多文化共生教育の推進など、短期・中期・長期にわたる包括的な取り組みが必要です。
差別のない社会を実現することは、外国人のためだけでなく、すべての人が尊厳を持って生きられる社会を作ることにつながります。多様性を認め合い、互いを尊重する社会こそ、持続可能で豊かな未来を築く基盤なのです。
次回は「政治参加と権利の問題」について詳しく見ていきます。
参考資料
- 法務省「外国人住民調査報告書」
- 国土交通省「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」
- 文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」
- 川崎市「差別のない人権尊重のまちづくり条例」
- ドイツ連邦差別禁止庁「年次報告書」
- カナダ人権委員会「Annual Report」