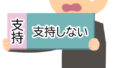2025年10月8日、日本中が歓喜に包まれました。京都大学の北川進特別教授が、ノーベル化学賞を受賞したのです。授賞理由は「金属有機構造体(MOF)の開発」。聞き慣れない言葉かもしれませんが、この研究は地球環境問題やエネルギー危機を解決する鍵として、世界中から注目を集めています。
革命的な素材「MOF」とは
北川さんが開発したMOF(金属有機構造体)は、金属イオンと有機分子を組み合わせて作られる多孔性材料です。簡単に言えば、原子レベルで設計された「分子の積み木」のようなもの。その最大の特徴は、無数の微小な穴があいた構造にあります。
この穴は、冷蔵庫の消臭剤に使われる活性炭の穴とは比べものになりません。MOFの表面積は1グラムあたり8,000平方メートルにも及び、これはサッカーコート約1面分に相当します。しかも、その穴の大きさや形を自在に設計できるのです。
まるでオーダーメイドの家を建てるように、取り込みたい物質に合わせて「分子の家」を設計できる。これがMOFの革新性です。
30年以上の挑戦が結実
北川さんの研究の歴史は1990年代後半に遡ります。当時、金属錯体を研究していた北川さんは、実験の待ち時間に結晶をじっと見つめ、そこに無数の穴が規則正しく並んでいることに気づきました。
「これは自分の研究人生が懸けられるテーマだ」
そう直感した北川さんは、以来30年以上にわたってこの研究に情熱を注ぎ続けました。学会では著名な研究者に対しても「理論的におかしい」と臆せず指摘する姿勢は、学生時代から変わらぬもの。誰も行ったことのない道を恐れずに進む勇気が、今回のノーベル賞につながったのです。
温かな人柄と教育哲学
研究室の学生たちからは「フランクなおっちゃん」と親しまれている北川さん。厳しい指導者というよりも、温かく見守る恩師として慕われています。
教え子の堀毛悟史教授は、留学中にわざわざ訪ねてきてくれた北川さんの言葉を今でも覚えています。
「しっかり研究をやっていたら、見てくれる人がいる」
押し付けず、若手の自主性を尊重しながらも、しっかりと支える。そんな教育スタイルが、多くの優秀な研究者を育ててきました。北川さんが学生たちに伝える「三つのC」——Courage(勇気)、Challenge(挑戦)、Capability(能力)——は、彼自身が体現し続けてきた姿勢そのものです。
MOFが変える未来の社会
では、北川さんの研究は私たちの生活をどう変えるのでしょうか。MOFの応用可能性は驚くほど幅広いのです。
地球温暖化対策
発電所や工場から排出される二酸化炭素をMOFで選択的に吸着し、回収することができます。カーボンニュートラル社会の実現に向けた切り札として期待されています。
次世代エネルギー
水素をMOFの穴に効率よく貯蔵できるため、水素エネルギーの実用化に大きく貢献します。低圧・常温での水素貯蔵が可能になれば、輸送や燃料電池への利用が飛躍的に進むでしょう。
水資源の確保
乾燥地帯で大気中のわずかな水分をMOFが吸着し、飲料水として回収する装置もすでに開発されています。水不足に悩む地域に希望をもたらす技術です。
有害物質の除去
工場から排出される有毒ガスや、環境汚染物質として問題となっているPFASなどをMOFで吸着・除去できます。
医療・創薬分野
薬物を効率的に体内の標的部位に届けるドラッグデリバリーシステムへの応用も研究されています。
触媒としての応用
MOFの規則的な空間を化学反応の「場」として利用することで、従来は困難だった選択的な化学合成が可能になります。
すでに始まっている実用化
MOFの実用化はすでに始まっています。アメリカでは半導体製造に使う有害ガスを安全に運搬するボンベに、イギリスでは果物の鮮度を保つための包装材に、日本ではタンクの腐食を防ぐコーティング材に応用されています。
レゾナックや三井金属といった日本企業も、北川さんとの共同研究を通じてMOFの産業応用を加速させています。化学メーカーやエネルギー企業、スタートアップ企業も、分離膜や水素吸着材、環境センサーなどの開発に取り組んでおり、研究から産業化への流れが具体化しつつあります。
京都から世界へ
北川さんは1951年、京都市下京区に生まれました。小学校の文集には「天気を支配できる研究者になりたい」と書いていたそうです。地元の京都市立塔南高校(当時は城南高校)を卒業後、京都大学工学部に進学。以来、京都を拠点に研究を続けてきました。
京都大学は、日本初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹をはじめ、多くの受賞者を輩出してきました。北川さんの受賞により、京都ゆかりの受賞者は17人になります。地元で育ち、地元で学び、そして世界を変える研究を成し遂げた——それが北川進という研究者の歩みです。
科学者の醍醐味は「挑戦」
記者会見で北川さんは「グレート!」と喜びを表現し、こう語りました。
「新しいことへのチャレンジこそが科学者の醍醐味です」
受賞決定の夜、キャンパスの門を出た北川さんを100人もの学生が拍手で迎えました。「北川先生、最高!」という声に、北川さんは笑顔で手を振り、「ありがとう」と応えました。その姿には、厳格な権威というよりも、学生たちと喜びを分かち合う温かな人柄がにじみ出ていました。
終わりに
北川進さんのノーベル化学賞受賞は、30年以上にわたる地道な研究の結晶です。誰も注目していなかった「穴」に可能性を見出し、それを「分子の建築」として昇華させた。その挑戦の精神と、若手を育てる温かな姿勢が、今回の栄誉につながりました。
MOFという「夢の材料」は、まさに今、実用化の幕を開けようとしています。地球環境問題からエネルギー危機、水資源の確保まで——私たちの未来を変える技術として、北川さんの研究は世界中で花開いていくことでしょう。
京都の地から世界へ。少年時代の夢を実現し、さらには地球の未来に貢献する。北川進さんの物語は、科学の力と人間の可能性を示す、希望に満ちたストーリーなのです。
本記事は2025年10月9日時点の情報に基づいています。