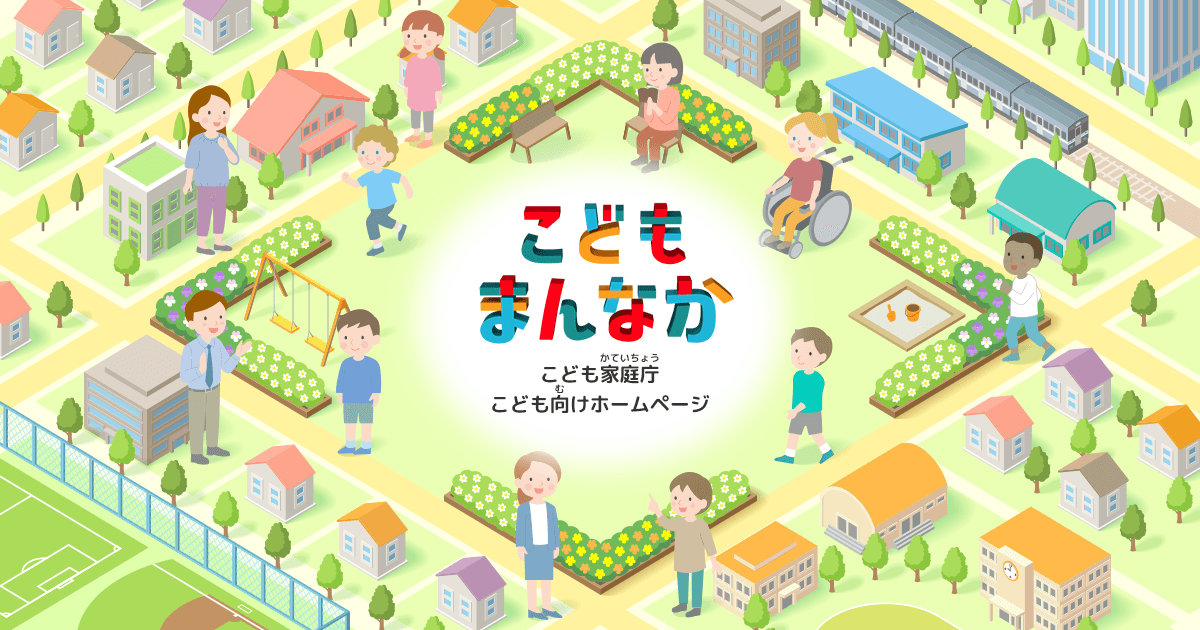日本が直面する最大の危機とも言われる少子化・人口減少。この問題に対応するため、2024年6月に「子ども・子育て支援金制度」を含む法律が成立しました。今回は、この制度の概要と、私たちの生活にどのような影響があるのかを詳しく解説します。
なぜ今、この制度が必要なのか
少子化・人口減少は我が国が直面する最大の危機であり、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスとされています。このような危機的な状況を受け、政府は2023年12月に「こども未来戦略」を閣議決定し、総額3.6兆円規模に及ぶ「こども・子育て支援加速化プラン」をまとめました。
この大規模な支援策を実現するためには、安定的な財源が不可欠です。そこで創設されたのが「子ども・子育て支援金制度」なのです。
支援金制度の基本的な仕組み
支援金制度は少子化対策のための特定財源であり、3.6兆円のうちの1兆円程度を確保します。この財源は、高齢者や事業主を含む全世代・全経済主体が負担する仕組みとなっています。
重要なポイントは、医療・介護の徹底した歳出改革と賃上げによる実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で導入することです。つまり、単純に負担が増えるのではなく、他の改革による負担軽減効果とバランスを取りながら実施されます。
支援金は、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出いただく形となり、令和8年度(2026年度)から令和10年度(2028年度)にかけて段階的に構築されます。段階的な構築までの間は、「子ども・子育て支援特例公債」(つなぎ公債)が発行され、必要な事業費が賄われます。
支援金で実施される具体的な支援内容
集められた支援金は、以下の6つの主要な事業に充てられます。
1. 児童手当の抜本的な拡充(2024年10月から)
所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額されます。これまで中学生までだった支給対象が高校生年代まで広がり、より多くの家庭が支援を受けられるようになりました。特に第3子以降への手厚い支援は、多子世帯の経済的負担を大きく軽減します。
2. 妊婦のための支援給付(2025年4月から制度化)
出産・子育て応援交付金として、妊娠・出産時に10万円の経済支援が提供されます。妊娠から出産にかかる費用負担を軽減し、安心して出産できる環境を整えます。
3. 乳児等のための支援給付(2026年4月から給付化)
「こども誰でも通園制度」として、月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みが創設されます。保育園の空きを待たずに、必要な時に一時的な保育サービスを利用できるようになります。
4. 出生後休業支援給付(2025年4月から)
子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付されます。経済的な不安を解消し、男性の育休取得促進にもつながることが期待されます。
5. 育児時短就業給付(2025年4月から)
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給します。キャリアを継続しながら育児との両立を目指す家庭を支援します。
6. 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置(2026年10月から)
自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除します。会社員だけでなく、自営業者やフリーランスの方々にも育児期間の経済的支援が広がります。
私たちにとっての意味
この支援金制度は、単なる子育て世帯への給付ではなく、「社会全体でこども・子育て世帯を応援していく」という理念に基づいています。少子化は社会全体の問題であり、その解決には全世代が協力する必要があるという考え方です。
確かに医療保険料と合わせた形で負担が求められますが、その負担は所得に応じたものとなっており、同時に医療・介護の歳出改革による負担軽減も図られます。そして何より、充実した子育て支援によって、若い世代が安心して子どもを産み育てられる社会の実現を目指しています。
今後のスケジュール
制度は段階的に実施されます。児童手当の拡充はすでに2024年10月から開始されており、2025年4月には出産・育休関連の給付が、2026年度からは「こども誰でも通園制度」や国民年金の保険料免除措置が始まります。そして2026年度から2028年度にかけて、支援金制度そのものが段階的に構築されていきます。
少子化対策は一朝一夕には実現できません。しかし、この支援金制度を通じて、すべての世代が協力しながら、未来を担う子どもたちを社会全体で支えていく——そんな新しい時代の始まりと言えるでしょう。